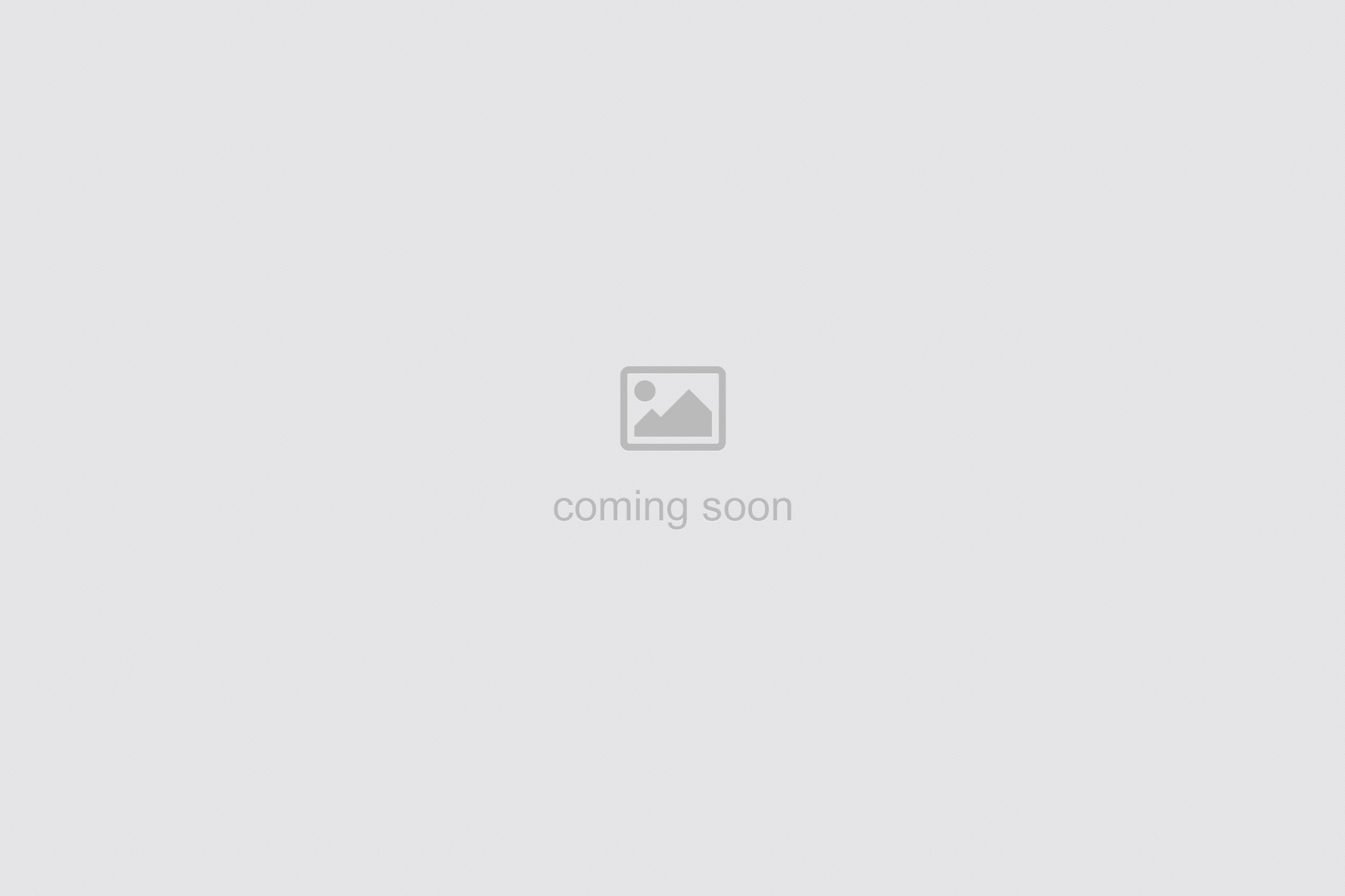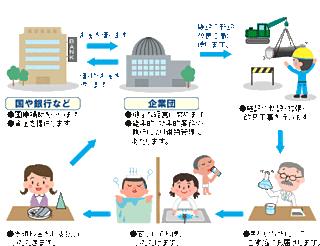水道事業経営の仕組み
地方公営企業法による経営
水道事業は、地方公営企業法という法律により、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとされています。この経済性と公共の福祉の増進という二つの要請をいかに実現していくかが水道事業の最も重要な課題です。
みなさんの生活にとって、必要不可欠で代替のきかない水を安全に安定的にお届けすることと、企業としての経済性を発揮して効率的な経営を図ることの両立を常に追求しています。
みなさんの生活にとって、必要不可欠で代替のきかない水を安全に安定的にお届けすることと、企業としての経済性を発揮して効率的な経営を図ることの両立を常に追求しています。
水道事業の経営は独立採算制です
水道事業の経営は、地方公営企業法によって「独立採算制」をとっています。みなさんがお住まいの市町村へ納めていただく税金ではなく、使用水量に応じて納入していただく料金収入で、すべての経費をまかなっています。これを「独立採算制」といいます。このことが、各市町村によって水道料金が異なる原因の一つになっています。
左の図のように、水道事業の通常業務にかかわる費用(人件費、光熱費、薬品代など)や建物・施設の修繕など維持管理費用はすべて、みなさんが納入していている水道料金によってまかなわれています。
また、みなさんの日々の暮らしに必要不可欠な安全、安心な水を安定的に送り続けるためには、浄水場、配水池、配水管など水道施設の建て替えや古くなった水道管の取替えなど、建設改良に伴う莫大な費用が必要となります。この資金については、自己財源を充て、不足する場合は、主に国からの借入金が充てられることになります。そして水道施設ができ、みなさんのご家庭へ水道の水をお届けし、お使いになった使用水量に基づいて水道料金をいただきます。
この料金収入の中から、毎年少しずつ借りたお金に利息を付けて返済しながら、水道の経営を行っています。
企業会計方式
水道事業の会計制度については、企業性を発揮するため、経営成績や財政状況を明確に把握できる企業会計方式を採用しています。
水道事業経営戦略(平成29年3月作成)
水道事業経営戦略 (1519KB) ○経営戦略策定の背景 ~現状と課題~
1事業の現況
これまでの主な経営健全化の取組
経営比較分析表を活用した現状分析
経営比較分析表
2将来の事業環境
給水人口の予測
水需要の予測
料金収入の見通し
施設の見通し
組織の見通し
3経営の基本方針
4投資・財政計画
投資・財政計画表
投資・財政計画の作成に当たっての説明
投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後の検討予定
5経営戦略の事後検証、更新等に関する事項
6参考資料
|
予算の概要
令和6年度 (339KB) |
決算の概要
令和4年度 (933KB) |
経営比較分析表
令和4年度 (182KB) |
資金不足比率の公表
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講じることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として、平成20年4月から施行されました。
この地方公共団体の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
この地方公共団体の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
年度別業務一覧
情報公開の運用状況
令和5年度 (36KB) |